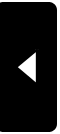PR
2014年09月11日
9月11日の記事
本日は、『相続対策③』についてを、お話させていただきます。
1・遺言
遺産分割がもめそうであると思われる様な時や、次のような特殊事情が有るときは、遺言は必須のものといえるかと思います。
(1)個人事業を承継させたい場合
個人事業を特定の者に継がせる場合には、たとえそれが遺産の大半であっても、事業関連資産はすべて承継者に相続させなければなりません。
そのような場合には、遺言で明白にそれを指示しておくべきでしょう。
(2)夫婦間に子がいないとき
子がいない場合に夫が死亡した場合には、妻が全財産を相続できるわけではありません。
多くの場合、妻は日頃疎遠にしていた夫の兄弟たちと、気苦労の多い遺産分割の折衝をしなければなりません。
これを防ぐには『配偶者に全財産を相続させる』との遺言が一番です。
兄弟達には遺留分がないため、この遺言で一件落着となるのです。
(3)内縁関係にある者
内縁とは、届出をしていない婚姻のことです。
要するに事実上の夫婦なのですが、主義主張その他の特殊事情から婚姻届を出していないのです。
ただしそうであるにしても、民法上は夫婦とは認められないためお互いに相続権はないわけです。
当然万一のことを考え、早いうちから遺言を作成しておくべきでしょう。
(4)亡父の親を扶けている子のない嫁
嫁入り先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡してしまったが、その嫁はそのまま高齢の夫の親を扶けつつ同居している、という話です。
この場合その義親に相続が発生しても、長男の嫁は相続人ではありません。
嫁に子供がいればその子が亡父の代襲相続人として多くを相続できましょうが、このままでは遺産に全く無縁な存在として放り出されかねません。
このような場合は是非とも遺言により、嫁に相応の財産を遺贈させるべきです。さらにいえば、このようなときこそ、その親と嫁が養子縁組をするのです。これで嫁の立場は安泰となるわけです。
(5)法定相続人がいない場合
ご承知のとおり天涯孤独の人が死亡すると、遺産は最終的に国庫に帰属することとなります。
であるならば、生前世話になった人や各種の施設へ遺贈した方が、せっかくの財産を有効に生かせるように思います。
それには遺言あるのみです。
まして老後の今日世話になっている人があれば、その人に遺贈する旨の遺言を作成し、これを見せたうえでその人にこの保管を託しておけば、両者の関係は一層円満なものとなりましょう。
(6)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に一人でも行方不明者がいる場合には、すんなり遺産分割協議はできません。
利害関係者が家庭裁判所に不在者財産管理を申請する等、面倒な手続きが必要となります。
このような場合にも遺言は必須となります。
(7)その他
この他、離婚、再婚を繰り返す等により親族関係が複雑である場合、相応の資産を有する人が比較的高齢になってから再婚する場合、さらには子を認知しようとする場合等、遺言は大きな力を発揮します。
一般に日本人は遺言を苦手とするようですが、このように必要と思われる遺言は積極的に行うべきと考えます。
以上、『相続税対策③』についてを、お話させていただきました。
1・遺言
遺産分割がもめそうであると思われる様な時や、次のような特殊事情が有るときは、遺言は必須のものといえるかと思います。
(1)個人事業を承継させたい場合
個人事業を特定の者に継がせる場合には、たとえそれが遺産の大半であっても、事業関連資産はすべて承継者に相続させなければなりません。
そのような場合には、遺言で明白にそれを指示しておくべきでしょう。
(2)夫婦間に子がいないとき
子がいない場合に夫が死亡した場合には、妻が全財産を相続できるわけではありません。
多くの場合、妻は日頃疎遠にしていた夫の兄弟たちと、気苦労の多い遺産分割の折衝をしなければなりません。
これを防ぐには『配偶者に全財産を相続させる』との遺言が一番です。
兄弟達には遺留分がないため、この遺言で一件落着となるのです。
(3)内縁関係にある者
内縁とは、届出をしていない婚姻のことです。
要するに事実上の夫婦なのですが、主義主張その他の特殊事情から婚姻届を出していないのです。
ただしそうであるにしても、民法上は夫婦とは認められないためお互いに相続権はないわけです。
当然万一のことを考え、早いうちから遺言を作成しておくべきでしょう。
(4)亡父の親を扶けている子のない嫁
嫁入り先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡してしまったが、その嫁はそのまま高齢の夫の親を扶けつつ同居している、という話です。
この場合その義親に相続が発生しても、長男の嫁は相続人ではありません。
嫁に子供がいればその子が亡父の代襲相続人として多くを相続できましょうが、このままでは遺産に全く無縁な存在として放り出されかねません。
このような場合は是非とも遺言により、嫁に相応の財産を遺贈させるべきです。さらにいえば、このようなときこそ、その親と嫁が養子縁組をするのです。これで嫁の立場は安泰となるわけです。
(5)法定相続人がいない場合
ご承知のとおり天涯孤独の人が死亡すると、遺産は最終的に国庫に帰属することとなります。
であるならば、生前世話になった人や各種の施設へ遺贈した方が、せっかくの財産を有効に生かせるように思います。
それには遺言あるのみです。
まして老後の今日世話になっている人があれば、その人に遺贈する旨の遺言を作成し、これを見せたうえでその人にこの保管を託しておけば、両者の関係は一層円満なものとなりましょう。
(6)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に一人でも行方不明者がいる場合には、すんなり遺産分割協議はできません。
利害関係者が家庭裁判所に不在者財産管理を申請する等、面倒な手続きが必要となります。
このような場合にも遺言は必須となります。
(7)その他
この他、離婚、再婚を繰り返す等により親族関係が複雑である場合、相応の資産を有する人が比較的高齢になってから再婚する場合、さらには子を認知しようとする場合等、遺言は大きな力を発揮します。
一般に日本人は遺言を苦手とするようですが、このように必要と思われる遺言は積極的に行うべきと考えます。
以上、『相続税対策③』についてを、お話させていただきました。
Posted by 荒木財産FP at
09:31│Comments(0)
2014年09月10日
備えあれば憂いなし・・・相続対策について②・・・
本日は、『相続対策②』について、お話させていただきます。
1・遺産分割
(1)遺産分割の重要性
前回のご説明は、相続税が課される人のみを対象とした話でした。
しかし相続税の課せられる人は死亡した人の全体からみれば20人に1人以下と極めて少数派なのです。
ただし、円満な相続(遺産分割)は、相続税の課されない大多数の人にも共通した極めて重要な課題です。
一つの例としまして、相応の資産価値を有する老夫婦の敷地に長男夫婦が両親の面倒を見る形ですむ一方、弟や妹は外に出ているというケースにおいて、主な資産がこの敷地だけという場合を考えてみましょう。
両親の死後には、おそらく考えられるのは次のようなケースとなるでしょう。
しかし、果たしてこれでよいのか?という問題です。
①長男が土地を相続。他の二人の相続財産はゼロ。
②兄弟妹の三人で、土地を共有で相続。長男夫婦がそのまま住み続ける。
③この土地を売却し、代金を三人で配分。長男はその資金等で小さい家(マンション)に買い換える。
どれをとっても、あまり芳しくないように思います。(この中では①がベター。とにかく②はお勧めできません)。
何とか事前(第一次相続開始の10年以上前の段階)に手を打っておきたいものです。
もしうまい手がないのであれば、皆で事前にどの方針でいくか、分配するのであればその比率をどうするのか、等について何らかの合意がほしいところです。
それさえあれば、各相続人やその家族は、前もって精神的な心づもりや金銭的準備ができるからです。
(2)代償分割の利用
上記(1)の例の解決のヒントとなるのが代償分割です。
代償分割とは、『長男が土地を単独で相続する代わり(代償として)、長男の固有資産である金銭を弟と妹に各1000万円ずつ支払う』といったものです。(これは土地の売買ではありません。代償分割はあくまで遺産分割のひとつとして民法が定めている手法ですから、妙な税は課されません)。
問題は、長男側にいくらの資金負担能力があるか、です。
兄弟間に信頼関係が確保されていれば、代償金は長期の年賦払いも可能です。
このように、長男の支払能力に応じた合理的な代償金を収受した以上、両親の面倒をみた長男が土地を一人占めしても、弟と妹は納得するのではないかと考えられるのです。
代償分割は、このような解決策に止まらず、相続手続きの便法(例えば、多くの金融機関に預けられた多種多様な預金はすべて配偶者がまとめて相続し、その代償として、他の相続人に代償金を払うことにする、等)や譲渡所得税の将来的な節税策としての利用も可能です。
遺産分割の問題は、代償分割の応用方法のいかんによってかなり解決できる余地があるように思われるのです。
以上、『相続税対策②についてお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・遺産分割
(1)遺産分割の重要性
前回のご説明は、相続税が課される人のみを対象とした話でした。
しかし相続税の課せられる人は死亡した人の全体からみれば20人に1人以下と極めて少数派なのです。
ただし、円満な相続(遺産分割)は、相続税の課されない大多数の人にも共通した極めて重要な課題です。
一つの例としまして、相応の資産価値を有する老夫婦の敷地に長男夫婦が両親の面倒を見る形ですむ一方、弟や妹は外に出ているというケースにおいて、主な資産がこの敷地だけという場合を考えてみましょう。
両親の死後には、おそらく考えられるのは次のようなケースとなるでしょう。
しかし、果たしてこれでよいのか?という問題です。
①長男が土地を相続。他の二人の相続財産はゼロ。
②兄弟妹の三人で、土地を共有で相続。長男夫婦がそのまま住み続ける。
③この土地を売却し、代金を三人で配分。長男はその資金等で小さい家(マンション)に買い換える。
どれをとっても、あまり芳しくないように思います。(この中では①がベター。とにかく②はお勧めできません)。
何とか事前(第一次相続開始の10年以上前の段階)に手を打っておきたいものです。
もしうまい手がないのであれば、皆で事前にどの方針でいくか、分配するのであればその比率をどうするのか、等について何らかの合意がほしいところです。
それさえあれば、各相続人やその家族は、前もって精神的な心づもりや金銭的準備ができるからです。
(2)代償分割の利用
上記(1)の例の解決のヒントとなるのが代償分割です。
代償分割とは、『長男が土地を単独で相続する代わり(代償として)、長男の固有資産である金銭を弟と妹に各1000万円ずつ支払う』といったものです。(これは土地の売買ではありません。代償分割はあくまで遺産分割のひとつとして民法が定めている手法ですから、妙な税は課されません)。
問題は、長男側にいくらの資金負担能力があるか、です。
兄弟間に信頼関係が確保されていれば、代償金は長期の年賦払いも可能です。
このように、長男の支払能力に応じた合理的な代償金を収受した以上、両親の面倒をみた長男が土地を一人占めしても、弟と妹は納得するのではないかと考えられるのです。
代償分割は、このような解決策に止まらず、相続手続きの便法(例えば、多くの金融機関に預けられた多種多様な預金はすべて配偶者がまとめて相続し、その代償として、他の相続人に代償金を払うことにする、等)や譲渡所得税の将来的な節税策としての利用も可能です。
遺産分割の問題は、代償分割の応用方法のいかんによってかなり解決できる余地があるように思われるのです。
以上、『相続税対策②についてお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月09日
備えあれば憂いなし・・・相続対策について①・・・
本日は、『相続対策①』について、お話させていただきます。
1・はじめに
昭和60年頃以降、平成4~5年までにかけて、実にさまざまかつ大量の相続税対策が行われました。
大きな原因のひとつに地価の高騰と路線価水準のアップを基因とする、相続税の実質的大増税があったように思われます。
相続税対策の大流行は、国税当局による各種の強力な規制を招来させました。
負担付き贈与の事実上の禁止、養子縁組の制限、自社株評価の改正。
きわめつけは路線価水準の大幅アップです。
]これらの規制により、従来はなばなしく行われていた対策は、ほとんど駄目になってしまったのです。
しかし、相続税対策を必要とする人たちは少なくありません。
さらには、相続税はかからないものの、遺産の分割を含め各種の相続関連手続きを、どのように行うのか、といった現実的問題もあります。
ところで、従来の相続税対策には、少なからぬ問題点があったように思います。
相続税対策は、ただ税金を減らせばいいというものではありません。
お年寄りやその相続人たちにとって、どのような相続(税)対策がいいのか。
こうした観点からのものが何より求められているのです。
2・対策の三つの順位
相続税には、重要性からみた優先順位があります。
けっしてこの順位を誤ってはなりません。
最優先すべきは何といっても円満な相続。
次に納税資金の確保。
そして最後にやっと節税対策が出てきます。
節税対策を他に優先して行うと、大きな不幸に陥りかねません。
以下、順次説明いたします。
(1)円満な相続
相続税対策の最優先事項は、当人の安定した生活と、相続人の円満な遺産分割です。
とりわけ後者は重要かつ現実的には油断のできない難題でもあります。
それにはまず、税引後の正味財産を、各相続人がそれぞれ納得できるような形でいかに配分するのか。
これを最初の段階で考えておく必要があります。
ここで重要なのは、当人の相続(一次相続)に続き、やがて発生する配偶者の相続(第二次相続)後における、次世代間の最終的な配分状況を想定したうえでこれを考えねばならない点です。
一次相続による分割は一時的なものにすぎないといえるからです。
何よりも、不動産を次世代である兄弟等が共有する形の遺産分割は避けねばなりません。
共有持分を取得した相続人は、他の相続人の合意なしに換金ができません。
兄弟間の共有は、後年の紛争の火種となるからです。
ただし換金予定のものの共有は問題ありません。
また被相続人の配偶者と子の共有も構いません。
その配偶者の第二次相続発生の際に、その子の単独所有となる遺産分割をすればよいのです。
いずれにしても、遺産分割のトラブルが生じたら、もはや一家の絆の修復は不可能となりかねまん。
この問題につきましては、次回、述べさせていただきます。
(2)納税資金の確保
今日、一定以上の資産家の相続税対策のメインテーマーは、この問題に移っています。
すなわち課せられた相続税をどうやって払うかなのです。
遺産10億円の相続で、税金が3億円だとしましょう。
この場合おそらく預貯金等の流動資産(死亡保険金を含む)は多くても1億円でしょう。
残りは、自宅アパート等で、通常右から左に売却できる更地等はほとんどないのです。
大量の底地や自社株があったりすると、一層の苦戦が予想されます。
以前の典型的な失敗例を紹介しましょう。
かなり広い超高級住宅地(評価額15億円見当)の古い自宅に住む老人と子供の相続税対策です。他に大きな資産はありません。
相談を受け金融マンの提案により、全額借入れにより5億円の高級賃貸マンションを敷地の中央にドカンと建てたのです。
これによって、6億円の予想相続税額を3億円に半減させたとして、その金融マンは胸を張ったそうです。
しかしその人に質問したいのです。
『残りの3億円はどうやって払うのですか?』と。(このような場合には、事前または事後的に敷地の一部を売却するより他ありません。一部売却が地形の面で無理であれば、全部を売って小さめの土地に買い替えるのです。)
遺産が何億円であろうが何十億円であろうが、その多くが預金であれば何の問題もないのです。
現実はおいそれと換金できそうにない資産が大半なのです。
大資産家の最も頭の痛いのがこの点なのです。
(3)節税対策
しんがりに、やっと相続税を減らすためのいわゆる節税対策が登場します。
確かに税額は少ない方がいいに決まっています。
やりようによってはかなり減らせる可能性があるのも事実です。
しかし上記(2)の失敗事例をみるまでもなく、節税対策は、円満な相続や納税資金の確保と矛盾してはならないのです。
さらに往々にして節税対策にはマイナス面も付随します。
各種のリスク(対策に用いた事業のリスク、地価下落のリスク、借入金の変動リスク等)やいろいろな費用負担(報酬や流通税)等です。
ご承知のようにバブル時代の対策は、右肩上がり経済を前提にこれらのリスクを甘くみたために、惨惨たる結果に陥った例が少なくありません。
しかし、必要以上に恐れることもありません。
まずはこれらは充分に考慮に入れて総合的に対策を検討することです。
そして各種の問題がクリアされたのであれば、そのときこそ積極果敢に対策を推進すべきなのです。
以上『相続税対策①』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・はじめに
昭和60年頃以降、平成4~5年までにかけて、実にさまざまかつ大量の相続税対策が行われました。
大きな原因のひとつに地価の高騰と路線価水準のアップを基因とする、相続税の実質的大増税があったように思われます。
相続税対策の大流行は、国税当局による各種の強力な規制を招来させました。
負担付き贈与の事実上の禁止、養子縁組の制限、自社株評価の改正。
きわめつけは路線価水準の大幅アップです。
]これらの規制により、従来はなばなしく行われていた対策は、ほとんど駄目になってしまったのです。
しかし、相続税対策を必要とする人たちは少なくありません。
さらには、相続税はかからないものの、遺産の分割を含め各種の相続関連手続きを、どのように行うのか、といった現実的問題もあります。
ところで、従来の相続税対策には、少なからぬ問題点があったように思います。
相続税対策は、ただ税金を減らせばいいというものではありません。
お年寄りやその相続人たちにとって、どのような相続(税)対策がいいのか。
こうした観点からのものが何より求められているのです。
2・対策の三つの順位
相続税には、重要性からみた優先順位があります。
けっしてこの順位を誤ってはなりません。
最優先すべきは何といっても円満な相続。
次に納税資金の確保。
そして最後にやっと節税対策が出てきます。
節税対策を他に優先して行うと、大きな不幸に陥りかねません。
以下、順次説明いたします。
(1)円満な相続
相続税対策の最優先事項は、当人の安定した生活と、相続人の円満な遺産分割です。
とりわけ後者は重要かつ現実的には油断のできない難題でもあります。
それにはまず、税引後の正味財産を、各相続人がそれぞれ納得できるような形でいかに配分するのか。
これを最初の段階で考えておく必要があります。
ここで重要なのは、当人の相続(一次相続)に続き、やがて発生する配偶者の相続(第二次相続)後における、次世代間の最終的な配分状況を想定したうえでこれを考えねばならない点です。
一次相続による分割は一時的なものにすぎないといえるからです。
何よりも、不動産を次世代である兄弟等が共有する形の遺産分割は避けねばなりません。
共有持分を取得した相続人は、他の相続人の合意なしに換金ができません。
兄弟間の共有は、後年の紛争の火種となるからです。
ただし換金予定のものの共有は問題ありません。
また被相続人の配偶者と子の共有も構いません。
その配偶者の第二次相続発生の際に、その子の単独所有となる遺産分割をすればよいのです。
いずれにしても、遺産分割のトラブルが生じたら、もはや一家の絆の修復は不可能となりかねまん。
この問題につきましては、次回、述べさせていただきます。
(2)納税資金の確保
今日、一定以上の資産家の相続税対策のメインテーマーは、この問題に移っています。
すなわち課せられた相続税をどうやって払うかなのです。
遺産10億円の相続で、税金が3億円だとしましょう。
この場合おそらく預貯金等の流動資産(死亡保険金を含む)は多くても1億円でしょう。
残りは、自宅アパート等で、通常右から左に売却できる更地等はほとんどないのです。
大量の底地や自社株があったりすると、一層の苦戦が予想されます。
以前の典型的な失敗例を紹介しましょう。
かなり広い超高級住宅地(評価額15億円見当)の古い自宅に住む老人と子供の相続税対策です。他に大きな資産はありません。
相談を受け金融マンの提案により、全額借入れにより5億円の高級賃貸マンションを敷地の中央にドカンと建てたのです。
これによって、6億円の予想相続税額を3億円に半減させたとして、その金融マンは胸を張ったそうです。
しかしその人に質問したいのです。
『残りの3億円はどうやって払うのですか?』と。(このような場合には、事前または事後的に敷地の一部を売却するより他ありません。一部売却が地形の面で無理であれば、全部を売って小さめの土地に買い替えるのです。)
遺産が何億円であろうが何十億円であろうが、その多くが預金であれば何の問題もないのです。
現実はおいそれと換金できそうにない資産が大半なのです。
大資産家の最も頭の痛いのがこの点なのです。
(3)節税対策
しんがりに、やっと相続税を減らすためのいわゆる節税対策が登場します。
確かに税額は少ない方がいいに決まっています。
やりようによってはかなり減らせる可能性があるのも事実です。
しかし上記(2)の失敗事例をみるまでもなく、節税対策は、円満な相続や納税資金の確保と矛盾してはならないのです。
さらに往々にして節税対策にはマイナス面も付随します。
各種のリスク(対策に用いた事業のリスク、地価下落のリスク、借入金の変動リスク等)やいろいろな費用負担(報酬や流通税)等です。
ご承知のようにバブル時代の対策は、右肩上がり経済を前提にこれらのリスクを甘くみたために、惨惨たる結果に陥った例が少なくありません。
しかし、必要以上に恐れることもありません。
まずはこれらは充分に考慮に入れて総合的に対策を検討することです。
そして各種の問題がクリアされたのであれば、そのときこそ積極果敢に対策を推進すべきなのです。
以上『相続税対策①』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月08日
備えあれば憂いなし・・・親族の借地関係について③・・・
今回は『親族間の借地関係③』についてを、お話させていただきます。
1.親族間の借地関係
(1)親の借地上への子の建築
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。
借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。
ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。
そこでAの子Bが資金を出します。
むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
こうした例は、少なくないものと思います。
この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。
借地権者はあくまで親Aのままなのです。
当事者は地主を含め皆そう認識しています。
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。
外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。
少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。
そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。
要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。
(2)子による底地の買取り
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。
いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。
そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。
土地は親への使用貸借になります。
つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。
すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。
『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
これも非現実的な話です。
そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。
要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.親族間の借地関係
(1)親の借地上への子の建築
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。
借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。
ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。
そこでAの子Bが資金を出します。
むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
こうした例は、少なくないものと思います。
この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。
借地権者はあくまで親Aのままなのです。
当事者は地主を含め皆そう認識しています。
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。
外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。
少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。
そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。
要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。
(2)子による底地の買取り
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。
いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。
そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。
土地は親への使用貸借になります。
つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。
すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。
『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
これも非現実的な話です。
そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。
要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月07日
備えあれば憂いなし・・・親族の借地関係について②・・・
本日は、『親族の借地関係②』についてを、お話させていただきます。
税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められる事となった経緯としましては、従来は『借地権なくして建物なし』というように、建物と借地権の両者をいわば糊付けした取扱いにしていました。
むろん『糊付け』された土地に関しては相続発生時には底地評価となります。
しかし、ある裁判で『糊付け論』が否定されました。
理由は『借地権とは,建物所有を目的とする土地の賃借権等である。
賃料を払っていない使用貸借における土地使用では、借地権が発生するはずがない』というものです。
この判決以降、税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められました。
その後は、親の土地に子供が家を建てることは、何の問題もなくなったのです。
もっとも、将来における相続発生時には、当然この土地の評価は更地評価(貸家建付地の減額も不可)となります。
使用貸借に供されている土地は事業用(賃貸用)でもなければ、(親の)居住用でもないものとされます。
理屈の上では確かにその取りなのですが、これにより事業用・居住用不動産に関する一切の特例(譲渡所得や相続税)から排除されてしまうのです。
さらに細かい点(相続税評価における評価単位等)に至るまで、この考え方が多岐にわたって浸透しています。
したがって、税務上の判断においては、土地の利用関係が賃貸借なのか使用貸借なのかを明らかにすることが先決となります。
同時に親族間における賃借では『賃料(家賃や地代)を払うべきかどうか』についても、しっかりした判断が求められます。
単に支払能力の有無等ではなく、税務上の取扱いの違いをしっかり見据える必要があるのです。
一つの例を示しましょう。
親の土地に子供が家を建てる場合です。
通常は土地は使用貸借となります。
しかし親の収入が少ないような場合には、生活費の援助を兼ねた形で、相応の地代を払おうとするケースもあるでしょう。
しかし、この場合は決して地代を払ってはなりません。
地代を払えば、土地の賃貸借となります。
一気に借地権の贈与とみなされてしまうのです。
いつ課税されてもおかしくない状況になってしまうわけです。
このような場合には、地代としてではなく、親の扶養としてお金を渡さなければなりません(なお、その土地の固定資産税額程度のものであれば、地代とはみなされません)。
以上、『親族の借地関係②』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められる事となった経緯としましては、従来は『借地権なくして建物なし』というように、建物と借地権の両者をいわば糊付けした取扱いにしていました。
むろん『糊付け』された土地に関しては相続発生時には底地評価となります。
しかし、ある裁判で『糊付け論』が否定されました。
理由は『借地権とは,建物所有を目的とする土地の賃借権等である。
賃料を払っていない使用貸借における土地使用では、借地権が発生するはずがない』というものです。
この判決以降、税務上で『建物所有を目的とする土地の使用貸借』が認められました。
その後は、親の土地に子供が家を建てることは、何の問題もなくなったのです。
もっとも、将来における相続発生時には、当然この土地の評価は更地評価(貸家建付地の減額も不可)となります。
使用貸借に供されている土地は事業用(賃貸用)でもなければ、(親の)居住用でもないものとされます。
理屈の上では確かにその取りなのですが、これにより事業用・居住用不動産に関する一切の特例(譲渡所得や相続税)から排除されてしまうのです。
さらに細かい点(相続税評価における評価単位等)に至るまで、この考え方が多岐にわたって浸透しています。
したがって、税務上の判断においては、土地の利用関係が賃貸借なのか使用貸借なのかを明らかにすることが先決となります。
同時に親族間における賃借では『賃料(家賃や地代)を払うべきかどうか』についても、しっかりした判断が求められます。
単に支払能力の有無等ではなく、税務上の取扱いの違いをしっかり見据える必要があるのです。
一つの例を示しましょう。
親の土地に子供が家を建てる場合です。
通常は土地は使用貸借となります。
しかし親の収入が少ないような場合には、生活費の援助を兼ねた形で、相応の地代を払おうとするケースもあるでしょう。
しかし、この場合は決して地代を払ってはなりません。
地代を払えば、土地の賃貸借となります。
一気に借地権の贈与とみなされてしまうのです。
いつ課税されてもおかしくない状況になってしまうわけです。
このような場合には、地代としてではなく、親の扶養としてお金を渡さなければなりません(なお、その土地の固定資産税額程度のものであれば、地代とはみなされません)。
以上、『親族の借地関係②』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月06日
備えあれば憂いなし・・・親族間の借地関係について・・・
今回は『親族間の借地関係』についてお話させていただきます。
1・使用貸借と賃貸借
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。
建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。
このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。
一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。
むろん地代はゼロです。
この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。
『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。
借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。
この場合はそれがない。
つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。
しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。
これには理由があるのです。
この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。
以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・使用貸借と賃貸借
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。
建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。
このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。
一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。
むろん地代はゼロです。
この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。
『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。
借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。
この場合はそれがない。
つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。
しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。
これには理由があるのです。
この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。
以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月05日
備えあれば憂いなし・・・生命保険の税務②・・・
本日は、『生命保険の税務②』についてを、お話させていただきます。
1・生命保険の税務関係
生命保険に関して保険事故の発生等何らかの動きがあると、その態様に応じて相続税や所得税(一時所得)、贈与税の課税関係が発生します。これらを各税目ごとにみていくこととします。
(1)相続税
税法が注目する保険料負担者(通常は保険契約者、以下保険契約者と表現します)が死亡した場合には、その相続人等に相続税が課されます。
典型的な場合は、保険契約者(すなわち保険料負担者)が被保険者になっている場合において、その人が死亡するケースです。(夫が自分を被保険者、妻や子を受取人として保険を契約した後、夫が死亡した場合)。
この場合、その死亡保険金がみなし相続財産として相続税が課されるパターンです(法定相続人1人500万円の非課税枠あり)。
一方、被保険者ではない保険契約者が死亡した(たとえば、孫を被保険者として祖父が保険を契約していたところ、その祖父が死亡した)場合には、死亡保険金は出ません。
しかし契約者としての地位(預金にたとえると預金者の立場)は誰かが継承します。すなわち、その承継者が生命保険契約の権利を相続したことになります。これに対して相続税が課されるわけです。
生命保険契約の権利とは、分かりやすく言えば契約を解約した場合の解約返戻金を受け取るこののできる権利です。
契約者はいつでも保険を解約することができるのです。
相続税の評価額は『解約返戻金』で評価することとなります。
(2)所得税
保険事故が発生した場合において、死亡保険金の受取人が保険契約者(保険料負担者)であった場合には、その受取人には所得税(一時所得)が課されます。
父を被保険者として、息子が自らを保険金受取人として保険料を払っていた場合に、父が死亡したというケースです。
この場合の息子は、自らの負担において自らが収入を得たわけですから、当然所得税の対象となるわけです。(実際の所得額は受取保険金から払込み保険料を控除した額をベースに計算する)。
なお仮にこのケースで、息子が保険料のうち6割を、被保険者である父が4割を負担していた場合には、その受取保険金のうち6割が所得税、4割が相続税の課税対象となります。
要するに保険料の負担割合によって課税されるわけです。
(3)贈与税
先の所得税は、負担者=受取人の場合でしたが、負担者≠受取人であればどうなるでしょうか。
この場合は、保険金(満期保険金を含む)を取得した保険金受取人は、保険料負担者から贈与により取得したこととされます。
受取人が何の負担もしないで保険金を取得しているわけですから、当然といえましょう。
しかし税率の高い贈与税をかけられたのではたまりません。
保険に入る場合には、この辺をよく考えて加入すべきでしょう。
なお、保険契約者を変更すると、従前の契約者から新契約者にこの生命保険契約の権利が贈与されたこととなります。
預金の名義をかえたことと同じことですから当然といえましょう。
例をあげますと、Aを被保険者、Bを保険金受取人、Cを保険契約者とした保険契約において、実際の保険料はAが5割、Bが3割、Cが2割を払っていたところ、保険事故が発生し、受取人であるBが1,000万円の死亡保険金を受け取りました。この課税関係はどうなるか、という話です。
答えは、500万円が相続税、300万円が所得税、200万円が贈与税の課税対象となります。
以上、『生命保険の税務②』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・生命保険の税務関係
生命保険に関して保険事故の発生等何らかの動きがあると、その態様に応じて相続税や所得税(一時所得)、贈与税の課税関係が発生します。これらを各税目ごとにみていくこととします。
(1)相続税
税法が注目する保険料負担者(通常は保険契約者、以下保険契約者と表現します)が死亡した場合には、その相続人等に相続税が課されます。
典型的な場合は、保険契約者(すなわち保険料負担者)が被保険者になっている場合において、その人が死亡するケースです。(夫が自分を被保険者、妻や子を受取人として保険を契約した後、夫が死亡した場合)。
この場合、その死亡保険金がみなし相続財産として相続税が課されるパターンです(法定相続人1人500万円の非課税枠あり)。
一方、被保険者ではない保険契約者が死亡した(たとえば、孫を被保険者として祖父が保険を契約していたところ、その祖父が死亡した)場合には、死亡保険金は出ません。
しかし契約者としての地位(預金にたとえると預金者の立場)は誰かが継承します。すなわち、その承継者が生命保険契約の権利を相続したことになります。これに対して相続税が課されるわけです。
生命保険契約の権利とは、分かりやすく言えば契約を解約した場合の解約返戻金を受け取るこののできる権利です。
契約者はいつでも保険を解約することができるのです。
相続税の評価額は『解約返戻金』で評価することとなります。
(2)所得税
保険事故が発生した場合において、死亡保険金の受取人が保険契約者(保険料負担者)であった場合には、その受取人には所得税(一時所得)が課されます。
父を被保険者として、息子が自らを保険金受取人として保険料を払っていた場合に、父が死亡したというケースです。
この場合の息子は、自らの負担において自らが収入を得たわけですから、当然所得税の対象となるわけです。(実際の所得額は受取保険金から払込み保険料を控除した額をベースに計算する)。
なお仮にこのケースで、息子が保険料のうち6割を、被保険者である父が4割を負担していた場合には、その受取保険金のうち6割が所得税、4割が相続税の課税対象となります。
要するに保険料の負担割合によって課税されるわけです。
(3)贈与税
先の所得税は、負担者=受取人の場合でしたが、負担者≠受取人であればどうなるでしょうか。
この場合は、保険金(満期保険金を含む)を取得した保険金受取人は、保険料負担者から贈与により取得したこととされます。
受取人が何の負担もしないで保険金を取得しているわけですから、当然といえましょう。
しかし税率の高い贈与税をかけられたのではたまりません。
保険に入る場合には、この辺をよく考えて加入すべきでしょう。
なお、保険契約者を変更すると、従前の契約者から新契約者にこの生命保険契約の権利が贈与されたこととなります。
預金の名義をかえたことと同じことですから当然といえましょう。
例をあげますと、Aを被保険者、Bを保険金受取人、Cを保険契約者とした保険契約において、実際の保険料はAが5割、Bが3割、Cが2割を払っていたところ、保険事故が発生し、受取人であるBが1,000万円の死亡保険金を受け取りました。この課税関係はどうなるか、という話です。
答えは、500万円が相続税、300万円が所得税、200万円が贈与税の課税対象となります。
以上、『生命保険の税務②』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月04日
備えあれば憂いなし・・・生命保険の税務・・・
さて、本日は『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきます。
1・生命保険の税務
(1)生命保険の仕組み
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。
貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。
さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。
死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。
さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。
これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。
・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。
・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。
・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)
・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。
次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。
・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。
保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。
以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・生命保険の税務
(1)生命保険の仕組み
生命保険は大きく分けて、定期保険と生存保険、そしてその両者が組み合わされた混合保険の3種類に区分されます。
定期保険とは、一定の期間に保険事故(死亡)が発生した場合に保険金が支払われるだけのものです。
貯蓄性がなく掛け捨て保険ともいわれ、その分保険料は低廉です。
生存保険とは、一定期間経過後に生存していた場合に、満期保険金が支払われるものです。一般に養老保険といわれかなり貯蓄性が高く、その分払い込む保険料も高くなっています。
一般に普及されている保険は、定期付養老保険といった両者の混合された保険です。
さらにこれに一定の障害の場合に特約を付ける等、これらの組み合わせ方を変えることによって、実にさまざまな保険が販売されているのです。
これらの保険は一定期間に限っての保険ですが、10数年前頃に死亡時点まで保険期間とする終身保険が開発されました。現在は定期付終身保険が主流になっています。
さて、保険に加入した場合に、生命保険会社から受けられるものには、次のようなものがあります。
死亡保険金、満期保険金、各種の特約に基づく給付金(入院給付金等)、保険会社を中途解約した場合の解約返戻金です。
さらには保険契約者は、保険会社から借り入れることもできます(契約者貸付)。
これらに対する税の取り扱いが、ここでの課題となっているわけです。
保険契約に関しての登場人物は次の通りとなります。
・保険契約者・・・保険会社と契約する人です。保険契約者は保険契約に関する全権を握っています。中途解約にて解約返戻金を手にすることや契約者貸付けを受けることもできます。保険金受取人を変えることもできます。
・被保険者・・・保険をかけられる人です。この人の状況によって支払うべき保険料の額が決定されます。むろん高齢者は高く、若い人であれば安くなります。したがって原則として契約の途中で被保険者を変更することはできません。
・保険金受取人・・・保険金を受け取ることのできる人です。受取人は甲60%、乙40%といった決め方もOK。死亡保険金の受取人はAで満期保険金はB、ということも可能です。受取人を途中で変更しても課税関係は発生しません。(課税は、実際に保険金が支給されてからの話なのです。)
・保険会社・・・保険業法に定められた生命保険会社です。
本来、保険契約の当事者間における登場人物はこの4者だけなのですが、税法は独自に隠れた主人公を登場させます。
次に掲げるこの人が出てくるために、課税関係が複雑になるのです。
・保険料負担者・・・保険料を実際に支払っている人です。本来これは契約者のはずです。保険会社も契約者が負担しているものとみなしており、保険証券への記載等保険会社には一切保険料負担者は登場しません。
確かに、世の中には妻が契約者である保険料を夫が払っているといった話は少なからずあります。いわば夫のお金を妻名義で預金している、ようなものでしょう。
保険においては、契約者以外の者が保険料を払った場合においても、その時点では課税関係は発生させません。
保険金の支払いがある等、実際にお金が動いたときに、初めて実際の負担者に応じた課税が行われていくのです。
以上、『生命保険の税務①』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月03日
備えあれば憂いなし・・・贈与税について③・・・
本日は、『贈与税③について』をお話させていただきます。
(1)その他のみなし贈与
以下に、各種のみなし贈与とされるものをいくつか列挙します。
ただしこれは常識的に当然と思われるものばかりです。税の根本は『常識』なのです。
①信託
信託とは、委託者(依頼者)の財産を処分すること等により、一定の目的のために、委託者(信託銀行等)に対して受益者(信託により利益を受ける人)のために財産権の管理または処分を行わせることをいうものとされています。
したがって、委託者以外の者が受益者となる信託行為(他益信託)があった場合には、受益者がその信託を受ける権利を、委託者から贈与により取得したものとみなされることになるのです。
なお、受益者が学術研究者や学資を受ける学生である等の、一定の公益を目的とする信託(公益信託)から交付される金品については、非課税とされています。
個人が特別障害者を受益者とする信託契約を信託銀行と締結した一定の特別障害者扶養信託に関しても、贈与税は課されません。
②負担付贈与
ローン付きのアパートの贈与といった負担付贈与があった場合には、贈与財産の時価から負担額(ローン残高等)を差し引いた価格に相当する財産の贈与があったものとみなされます。
負担付贈与は、事実上低額譲受けと、その実態は同じです。税務上も同様の取扱いをしているわけです。
③共有持分の放棄
共有財産における共有持分の放棄は、その持分が他の共有者に対してその持分に応じて贈与されたものとみなされます。
④財産分与
離婚による財産分与によって取得した財産は、贈与税は課されません。
しかし、その分与財産の額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には、その部分は課税対象となります。
以上、『贈与税③』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
(1)その他のみなし贈与
以下に、各種のみなし贈与とされるものをいくつか列挙します。
ただしこれは常識的に当然と思われるものばかりです。税の根本は『常識』なのです。
①信託
信託とは、委託者(依頼者)の財産を処分すること等により、一定の目的のために、委託者(信託銀行等)に対して受益者(信託により利益を受ける人)のために財産権の管理または処分を行わせることをいうものとされています。
したがって、委託者以外の者が受益者となる信託行為(他益信託)があった場合には、受益者がその信託を受ける権利を、委託者から贈与により取得したものとみなされることになるのです。
なお、受益者が学術研究者や学資を受ける学生である等の、一定の公益を目的とする信託(公益信託)から交付される金品については、非課税とされています。
個人が特別障害者を受益者とする信託契約を信託銀行と締結した一定の特別障害者扶養信託に関しても、贈与税は課されません。
②負担付贈与
ローン付きのアパートの贈与といった負担付贈与があった場合には、贈与財産の時価から負担額(ローン残高等)を差し引いた価格に相当する財産の贈与があったものとみなされます。
負担付贈与は、事実上低額譲受けと、その実態は同じです。税務上も同様の取扱いをしているわけです。
③共有持分の放棄
共有財産における共有持分の放棄は、その持分が他の共有者に対してその持分に応じて贈与されたものとみなされます。
④財産分与
離婚による財産分与によって取得した財産は、贈与税は課されません。
しかし、その分与財産の額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合には、その部分は課税対象となります。
以上、『贈与税③』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月02日
備えあれば憂いなし・・・贈与税について②・・・
さて、本日は『贈与税②』についてお話させていただきます。
1・みなし贈与財産
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。
相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。
したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。
以下の『みなし贈与財産』がそれです。
(1)定額譲受け
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。
極めて当然のことといえましょう。
なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。
税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。
一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。
もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。
相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。
父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。
結論は400万円です。
要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。
つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。
事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。
公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。
『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。
しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。
(2)債務免除
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。
これも当然の規定といえましょう。
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。
保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。
また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。
以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・みなし贈与財産
税法は、贈与税の課税対象を単なる民法の定める贈与に限定していません。
相続税の補完税としての任務を果たすには、民法上の贈与という狭い枠に止まっていられなのです。
したがって民法上の贈与以外の実質的な贈与を、贈与とみなして課税対象としたわけです。
以下の『みなし贈与財産』がそれです。
(1)定額譲受け
著しく低い価格の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価との差額が贈与されたものとみなして贈与税が課されます。
極めて当然のことといえましょう。
なおこの『著しく低い』かどうかは、社会通念に従い判断されますが、やはり親族間ではシビアにみられるものと思われます。
ここで問題となるのは、贈与税計算のベースとなる『時価』とは何かです。
税法においては、いろいろなケースで時価(価格も同義語)という用語が出てきますが、その意味するところは微妙に違うのです。
相続・贈与税の場合には、時価は2通りの意味があります。
一つは建前としての評価、すなわち相続税評価額。
もう一つは、本当の時価(自由な経済取引の下で成立する取引価格)です。
相続税評価額は、本当の時価よりやや堅め(低め)に評価されています。
さて、ここは大切かつまぎらわしいところですから、事例で説明させていただきます。
父親が時価(公示価格ベース)1,000万円、相続税評価額800万円(公示の8割水準)の更地を、息子に600万円という著しく低い対価で譲渡したというケースの場合です。
この場合に贈与とみなされる金額は、1,000万円との差額の400万円か、800万円との差額の200万円か、という話です。
結論は400万円です。
要するに低額譲受けの場合の時価は、本当の時価を基準とするのです。
ただし、父親がこの土地を息子に贈与(対価はゼロ)した場合には、原則どおり相続評価額である800万円が課税対象となります。
つまり、一部でも対価を払う(すなわち低額譲受け)と、基準が本当の時価になってしまうのです。
ところで、実務上最も問題となるのは、『時価がいくらなのか』という点です。
事実不動産の時価は、たとえて言うならストライクゾーンのように一定の幅があるものなのです。
公示価格にしても、その幅の中のひとつの数値にすぎません。
まず、言える事は、路線価評価額(諸調整率適用後)を0.8で割り戻した額が一つの基準となることです。
『公示価格が時価であることと、路線価は公示価格の8割水準にあること』が一つの基準となっています。
しかし、この『路線価÷0.8』では実勢相場にそぐわないと思われる様な場合には、安易に当事者間で価格を決めずに不動産鑑定士や税理士等の専門の方に相談された方がよろしいかと思います。
(2)債務免除
債務の免除や、第三者のためにする債務の弁済等により利益を受けた場合は、これらの利益に相当する贈与があったものとみなして、贈与税が課されます。
これも当然の規定といえましょう。
また、連帯債務者が自己の負担すべき債務の部分を超えて弁済し、かつそれによって得た他の連帯債務者に対する求償権を放棄した場合には、贈与があったものとみなされます。
保証人が保証債務を履行したうえで、主たる債務者に対する求償権を放棄した場合も同様です。
ただし、これらの場合においても、その債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるときは、その困難とされる部分に対しては贈与税は課されません。
また、資力を喪失した債務者の扶養義務者がその債務の引受けや弁済を行った場合にも贈与税は課されない(逆に一般の人が債務引受けを行うと課税対象となる)こととされています。
以上、『贈与税②について』をお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
2014年09月02日
備えあれば憂いない・・・贈与税について①・・・
本日は、『贈与税①』についてお話させていただきます。
1・贈与税とは
(1)相続税の補完税
贈与税は、相続税を補完するための税として設けられたものです。
すなわち贈与税がなかったならば、あらかじめ生前に子供達に財産を贈与して将来の相続財産を減らすことにより、相続税の負担を軽減することができてしまうからです。
要するに、贈与税は相続税を徴収するための手段なのです。
むろんこの点だけではなく、贈与を受けた者(受贈者)の担税力の増加に着目しての課税、という側面もあります。
したがって、ともすると『贈与所得』といった所得税の対象にもなりうるわけですが、贈与税の課税対象とされていることから、所得税の課税対象外となっているわけです。(二重課税の排除)。
しかし、基本はあくまで相続税の補完税です。
そもそも、贈与税は相続税法の一部として定められています。
贈与税法という法律はないのです。(この点を称してよく『1税法2税目』といいます。ひとつの税法に2種類の税が定められている、という意味です)。
したがって、税の扇の要である税率をはじめ、多くが相続税との関連で規定されています。
贈与財産の評価も相続税評価で行います。
贈与税は、個人が個人から贈与を受けた場合に課される税です。
したがって、個人が法人から贈与を受けた場合には、贈与税の対象外です。
むろん非課税というわけではなく、所得税(一時所得)が課されます。
理由は、贈与する法人は相続税と無縁の存在であり、これを補完する必要がないからです。
一方、法人が贈与を受けた場合には、法人税(受贈益)が課されます。
ただし、一般に法人税が課されていない人格のない社団(PTA他)等が個人から贈与を受けた場合には、その社団等は個人とみなされて贈与税が課されます。
(2)贈与とは
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課税されます。
この場合贈与とは、民法上の贈与をいいます。
すなわち、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいうのです。(民法549条)
しかし、贈与税は単に民法上の贈与のみならず、実質的に贈与と同様の効果を有する行為についても、みなし贈与として課税対象に含めています。(みなし贈与については、次回、お話させていただきます。)
ところで、本来の贈与であっても、その贈与の事実の把握には困難が伴います。
そもそも贈与であるのかそうでないのか、その贈与はいつ行われたか、が定かでなかったり、贈与税を免れるために外見上は贈与でない体裁をとっていたり、と課税実務上その判定が難しいのです。
しかし、これらに対し手をこまねいてはいられません。まずは外観を重視して課税を行っていくのです。
たとえば、対価の授受がないまま不動産や株式等の名義が変更された場合には、原則として贈与があったものと取扱います。
当事者から、『いや単に名義を移しただけであって、真の権利者は元の名義人であり、贈与はしていない』という理屈の下に、贈与税を免れようとする主張がなされる可能性がありましょう。
しかしこのような場合には、課税実務上、名義変更という外観によって贈与を認定するのです。
ただし中には、納税者のこの主張が正しい場合もあるでしょう。その場合には、納税者が税務署に対して贈与ではない』旨の説得や立証を行う必要があります。
税務署がこれに納得すれば課税は行われないこととなるわけです。
以上、『贈与税①』についてお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・贈与税とは
(1)相続税の補完税
贈与税は、相続税を補完するための税として設けられたものです。
すなわち贈与税がなかったならば、あらかじめ生前に子供達に財産を贈与して将来の相続財産を減らすことにより、相続税の負担を軽減することができてしまうからです。
要するに、贈与税は相続税を徴収するための手段なのです。
むろんこの点だけではなく、贈与を受けた者(受贈者)の担税力の増加に着目しての課税、という側面もあります。
したがって、ともすると『贈与所得』といった所得税の対象にもなりうるわけですが、贈与税の課税対象とされていることから、所得税の課税対象外となっているわけです。(二重課税の排除)。
しかし、基本はあくまで相続税の補完税です。
そもそも、贈与税は相続税法の一部として定められています。
贈与税法という法律はないのです。(この点を称してよく『1税法2税目』といいます。ひとつの税法に2種類の税が定められている、という意味です)。
したがって、税の扇の要である税率をはじめ、多くが相続税との関連で規定されています。
贈与財産の評価も相続税評価で行います。
贈与税は、個人が個人から贈与を受けた場合に課される税です。
したがって、個人が法人から贈与を受けた場合には、贈与税の対象外です。
むろん非課税というわけではなく、所得税(一時所得)が課されます。
理由は、贈与する法人は相続税と無縁の存在であり、これを補完する必要がないからです。
一方、法人が贈与を受けた場合には、法人税(受贈益)が課されます。
ただし、一般に法人税が課されていない人格のない社団(PTA他)等が個人から贈与を受けた場合には、その社団等は個人とみなされて贈与税が課されます。
(2)贈与とは
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課税されます。
この場合贈与とは、民法上の贈与をいいます。
すなわち、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいうのです。(民法549条)
しかし、贈与税は単に民法上の贈与のみならず、実質的に贈与と同様の効果を有する行為についても、みなし贈与として課税対象に含めています。(みなし贈与については、次回、お話させていただきます。)
ところで、本来の贈与であっても、その贈与の事実の把握には困難が伴います。
そもそも贈与であるのかそうでないのか、その贈与はいつ行われたか、が定かでなかったり、贈与税を免れるために外見上は贈与でない体裁をとっていたり、と課税実務上その判定が難しいのです。
しかし、これらに対し手をこまねいてはいられません。まずは外観を重視して課税を行っていくのです。
たとえば、対価の授受がないまま不動産や株式等の名義が変更された場合には、原則として贈与があったものと取扱います。
当事者から、『いや単に名義を移しただけであって、真の権利者は元の名義人であり、贈与はしていない』という理屈の下に、贈与税を免れようとする主張がなされる可能性がありましょう。
しかしこのような場合には、課税実務上、名義変更という外観によって贈与を認定するのです。
ただし中には、納税者のこの主張が正しい場合もあるでしょう。その場合には、納税者が税務署に対して贈与ではない』旨の説得や立証を行う必要があります。
税務署がこれに納得すれば課税は行われないこととなるわけです。
以上、『贈与税①』についてお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)